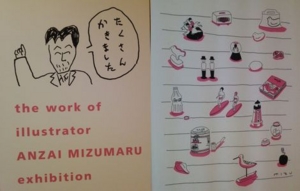勅使河原宏監督の「アントニー・ガウディ―」。武満徹の音楽が美しく、ビデオジャケットに記されているようにまさに映像詩的作品。宮口精二氏のナレーション(ごく最小限)。時代の潤沢さも感じる。サクラダ・ファミリア以外にもグエル氏のための仕事*1など紹介されており、興味深くおもしろかった。自然に沿ったようなまっすぐでない柱、そして凝った装飾・・よくこんなものを作るな・・という感想。でもあたたかみがあり、縄文文化に感じるようなものを同時に感じる。映像で未だ建設途中のサクラダ・ファミリアをみていたら、大阪に来ているブリューゲルの「BABEL」展のポスターを思い出してしまい、前からすすめれられてもいたので行ってみる。
公式サイト
聖書の中のバベルの塔の物語から、サクラダ・ファミリアを想像したら失礼な感じなんだけど、(教会だし)、ブリューゲルの展覧会では、BABELは人間の協力の姿がみられますというような解説もされていた。窓の形式が違うところに何年もの時代が流れたということを表現しているらしい。まさにサクラダ・ファミリアな・・
ネーデルランドの画家たちの活躍という事で祭壇彫刻の展示もあったが、これまたガウディ―の映画を思い出すようなところもあり・・
展覧会では、奇想ということでの先人ヒエロムニス・ボスの油彩も2点紹介されており、ボスの系列の方がボス風に描いた作品も紹介されていたがなかなかおもしろかった。ブリューゲルも、奇妙なクリーチャー的なものが出てくる作品群が楽しめる。
夏にヒグチユウコさんがブリューゲルの「BABEL」からインスパイアされた「BABEL」という画集の原画展にいったのだけど、改めてこの展覧会をみてから、ヒグチさんの「BABEL]をみると、オリジナルがわかってさらに楽しい。
[asin:B000064PN4:detail]
[asin:4766129938:detail]